蒸気加熱で多く利用される湿り蒸気について、工場等判断基準の基準部分(工場)では、乾き度を適切に維持することが定められている。
蒸気の変化
蒸気は加熱を続けると次のように変化していく。
- 湿り蒸気(飽和水+乾き飽和蒸気)
- 飽和蒸気
- 過熱蒸気
湿り蒸気
水を圧力一定で加熱すると温度が上昇するが、ある温度(=飽和温度)に達すると温度上昇が止まり、蒸気が発生し始める。
蒸気発生の開始直後は、飽和温度の水と蒸気が共存する。
飽和温度の水を飽和水、飽和温度の蒸気を乾き飽和蒸気と呼ぶ。
これらが混合した状態が湿り蒸気である。
飽和蒸気
湿り蒸気を加熱し続けると飽和水が減少し、蒸気は増加を続ける。
全体が「飽和温度の蒸気(=乾き飽和蒸気)」となった状態を飽和蒸気ともいう。
過熱蒸気
飽和蒸気(=全体が乾き飽和蒸気)をさらに加熱すると、蒸気は再び温度上昇を始める。
飽和温度以上となった蒸気を過熱蒸気という。
乾き度とは
上述のとおり、湿り蒸気は飽和水と乾き飽和蒸気をからなり、その混合割合で蒸気全体の性質が大きく異なる。
湿り蒸気=飽和水+乾き飽和蒸気
ここで、乾き度とは、湿り蒸気全体のうち、乾き飽和蒸気の占める質量の割合のことである。
乾き度をxとすると、
湿り蒸気の質量:乾き飽和蒸気の質量=1:x
たとえば、湿り蒸気1kgに乾き飽和蒸気0.6kgを含む場合、乾き度は0.6となる。
なお、飽和水の質量割合を湿り度と呼び、この例では湿り度は0.4となる。(1-0.6=0.4)
文献
R2 問題3 (6)
一般社団法人省エネルギーセンター編『改訂6版 エネルギー管理士試験講座エネルギー総合管理及び法規』一般社団法人省エネルギーセンター(2022)
p175「(1)蒸気の性質」

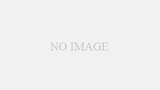
コメント