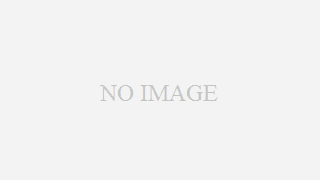 再生可能エネルギー
再生可能エネルギー 再生可能エネルギーで安定して大電力を得られない理由
再生可能エネルギーの課題として、安定して大電力を得られないことが広く知られています。太陽光や風力は自然エネルギーですので、自然環境に左右されます。発電電力が急に変動することもあります。たとえば仮に、電力系統の需要の大半を、太陽光パネルによっ...
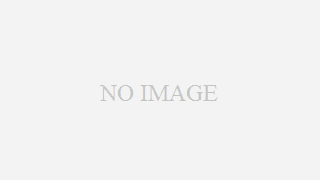 再生可能エネルギー
再生可能エネルギー 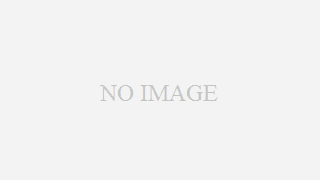 再生可能エネルギー
再生可能エネルギー 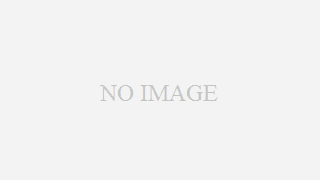 再生可能エネルギー
再生可能エネルギー 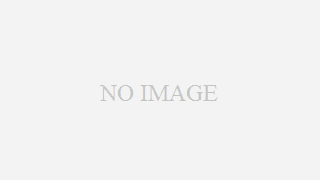 再生可能エネルギー
再生可能エネルギー 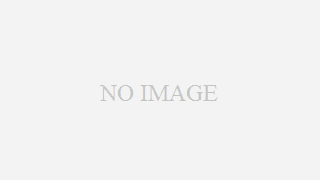 空気調和
空気調和 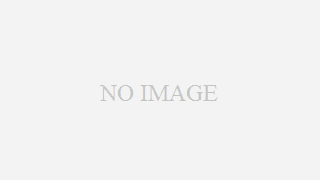 空気調和
空気調和 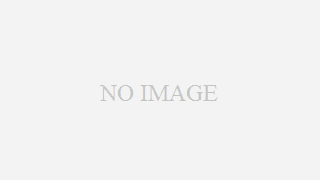 空気調和
空気調和 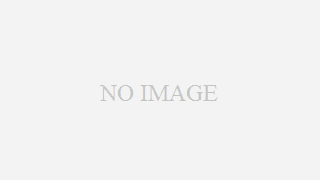 照明
照明 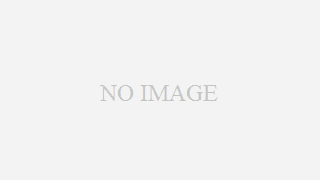 照明
照明 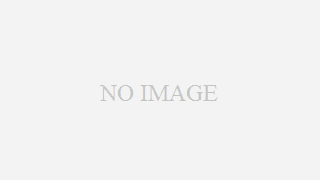 照明
照明