送電鉄塔と送電線の間に、お皿のような白い物体がついているのをみて、「あれはなんだろう?」と疑問に思ったことはないでしょうか。
お皿のような物体を「がいし」といいます。
本記事では「がいし」についてまとめます。
がいしの役割
送電線には、大きいものでは500,000V(50万ボルト)など、小さいものでも66,000Vなどの電圧がかかっています。
一方で、鉄塔は地面に脚をつけています。
もし電圧のかかった送電線を、鉄塔に直接、取り付けてしまったらどうなるでしょうか。
鉄塔に電気がきてしまいますね。
これでは送電できなくなってしまいます。
そこで「がいし」を使用することで、電線と地面を電気的に絶縁たうえで、電線を支えているのです。
「がいし」に求められる性能
次に、「がいし」に求められる性能を解説します。
機械的強度
がいしは、力のかかる電線を支えますから、十分な機械的強度(物理的な強さ)が必要です。
電線にかかる力にはどのようなものがあるでしょうか。
ひとつには、自重があります。電線自身の重さです。
鉄塔と鉄塔の間の距離(径間)は、たとえば400mなどに及ぶこともありますから、電線の自重を支えるだけでも相当な強度が必要になりそうですね。
他には、風や雪などによる外力があります。
こちらも、長い電線に力がかかりますから、相当な強度が必要になりそうですね。
がいしは、自重だけでなく、風や雪などによる外力にも耐えられる機械的強度を有することが求められます。
絶縁性能
がいしには、電気的な絶縁性能が求められます。
電線には、常時、大きな電圧がかかっています。
そのため、まずは、大きな電圧に長期間耐えられる絶縁性能が必要になりますね。
ただ、これだけではありません。
たとえば送電線や鉄塔に落雷があったときには、さらに電圧が上昇します。
異常時に上昇した電圧にも耐えなくてはなりません。
さらに、送電線・鉄塔は過酷な自然環境の中に設置されます。
雨や雪、霧などに対しても、十分な電気的絶縁性能を有する必要があります。
がいしは、普段の電圧に耐えるだけでなく、異常時や過酷な自然環境にも耐えられる絶縁性能が必要とします。
耐汚損性能
送電線は、海岸付近や、ばい煙の多い工業地帯などに設置されることもあります。
汚損の厳しい地帯です。
汚損は、電気的な絶縁性能を低下させます。
たとえば、塩分は電気を通します。
この塩分が「がいし」の表面に付着してしまったらどうなるでしょうか。
電線に流れる電気が、塩分の付着した「がいし」表面を経由し、鉄塔に流れ込んでしまいますね。
これでは困ります。
そこで、がいしの裏面に大きな「ひだ」をつけます。
大きなひだをつけることで、がいしの表面積が大きくなり、次のメリットが得られます。
- 塩分やほこりなどの汚れが付着しにくい
- 汚れを雨で洗い流しやすい
- 電気的な距離が大きくなることで、汚れても地面との絶縁を保つことができる
その他 性能
長期間の使用に対しても、電気的および機械的な性能の劣化が少ないことが重要となります。
過酷な自然環境の中で使用されますから、温度の急変にも耐えられることが必要です。
また、湿気を吸収すると絶縁性能が下がりますから、湿気を吸収しないことも重要です。
さらに、がいしはたくさん設置されますから、価格が安いことも求められます。
補足:「がいし」の色について
冒頭で、がいしの色を「白い」と書きました。
しかし景観への配慮から、茶色などが使用されることもあります。
特に山の中においては、茶色の「がいし」を見かけることも多いかと思います。
おわりに
本記事では、送電鉄塔についている「がいし」についてまとめました。

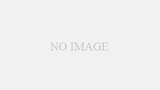
コメント